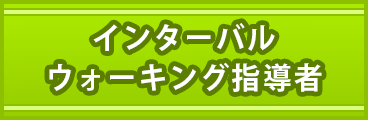全身の細胞の中では酵素を使って生化学反応が起こっています。酵素は化学反応を盛んにする触媒のような役割をしています。酵素による生化学反応は神経細胞でも同じことですが、生化学反応を起こすためには細胞の中で作り出されるエネルギーが必要になります。
神経細胞は長い形をしていて、神経細胞は受けた刺激は細胞内では電気信号として流れ、神経細胞の端(神経端末のシナプス)までくると神経伝達物質が放出されます。神経伝達物質は隣接しているシナプスが受け取り、これを電気信号に変えて神経細胞内を移動して、再びシナプスからシナプスへと神経伝達物質のバトンタッチによって、情報が伝えられていきます。
この流れがスムーズに進むためには、神経細胞で作られる神経伝達物質の量が重要になります。神経伝達物質は興奮系のドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリン、アセチルコリン、グルタミン酸などがあり、抑制系としてはセロトニン、GABA、グリシンなどがあります。
興奮系の神経伝達物質は年齢を重ねても大きくは減少しないのに対して、抑制系の神経伝達物質は減少しやすくなっています。そのため年齢を重ねると興奮を抑制できなくなり、精神面での安定が保ちにくくなり、自律神経の調整もつきにくくなります。
自律神経の交感神経は興奮系、副交感神経は抑制系となっています。消化、吸収、血液循環、排泄などの機能を高めるのは副交感神経の役割です。これらの機能が年齢を重ねると低下していくのは副交感神経の働きが低下するためであり、神経細胞の中で作られるエネルギーが減ったために抑制系の神経伝達物質の量が減ることが関係しています。
エネルギー代謝を高めることは、神経伝達の低下を防ぎ、できるだけ正常に保つための重要な手段になるのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕