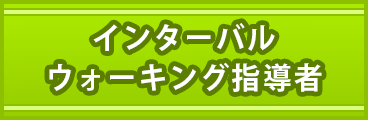エネルギー代謝を高める成分の代表といえば、コエンザイムQ10、L‐カルニチン、α‐リポ酸で、これらは代謝促進成分と呼ばれています。3種類の成分を、この順番で並べたのは、食品の成分として認められた順番だからです。以前は医薬品の成分だったのですが、2001年にコエンザイムQ10が、2002年にL‐カルニチン、2004年にα‐リポ酸が厚生労働省によって食品に使用することが許可されました。
コエンザイムQ10はエネルギー代謝が行われる細胞のミトコンドリアの最終段階でエネルギー化するときに使われる補酵素です。L‐カルニチンは脂肪酸をミトコンドリアに取り込むために必要な成分で、α‐リポ酸はエネルギー源(糖質、脂質、たんぱく質)をミトコンドリアで使われる高エネルギー化合物のアセチルCoAに変化させるときに使われる酵素の活用を進める成分です。
医薬品の成分というと化学合成されたものという印象が抱かれることがありますが、代謝促進成分は食品に含まれる成分です。今では当たり前に食品の成分と認識されているビタミン、ミネラル、アミノ酸も医薬品の成分としてしか使えない時代もありました。それが規制緩和によって、食品として使えるようになったものも多いのです。
3種類の代謝促進成分は、それぞれ医薬品の成分であったことから、有効性は認められていると考えられているものの、医薬品と同じ使い方をされているのはL‐カルニチンだけです。
医薬品の成分としてのL‐カルニチンはカルニチン欠乏症という体内でのL‐カルニチンの合成量が少ないためにエネルギー代謝が低下している人のために使われています。食品の成分としてのL‐カルニチンは、年齢を重ねるにつれて低下してくるL‐カルニチンの体内合成を補って、代謝の若返りを目指しているものです。
L‐カルニチンの研究データを厚生労働省に提供して、食品の成分として認められるように動いたのはロンザ社で、同社のL‐カルニチンは国内シェアの8割を占めています。このL‐カルニチンは有効性が確認されたものということで、どこのL‐カルニチンなのかを確認することも重要です。
コエンザイムQ10の研究データを提供したのは、還元型コエンザイムQ10で有名なカネカで、国内シェアの9割を占めています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕