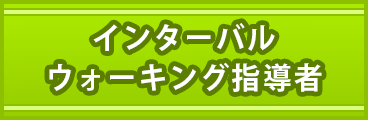発達障害者の支援は、発達障害がある人への直接的な支援だけでなく、その人が発達障害者として生きにくい状況を作り出している社会的障壁を取り除くことも同時に行う必要があります。これについては発達障害者支援法の第二条の二に「基本理念」として示されています。
基本理念の初めには、「発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行わなければならない。」と書かれています。
この中で注目されるのは「地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」という部分で、共生することが妨げられるようなことがあってはいけないということが述べられています。
これを受けて、「発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行わなければならない。」と書かれています。発達障害がある人への支援というと、その状態が明らかになったときに初めて支援として実施される発達障害児支援施設が思い浮かべられることが多くなっています。その施設での支援が主となっているように思われがちですが、この支援によって状態が改善されたとしても、それは個人の状態の改善にとどまっています。
その支援の内容については、「発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。」と書かれています。
この支援によって状態の軽減などの改善がみられたとしても、社会的障壁が改善されていなければ、発達障害者支援法が目指している発達障害がある人の本当の意味での支援にはなっていないということが示されているのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕