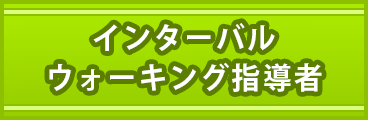職場が消滅するということは考えてもいないし、考えたくもないというのは当たり前の気持ちです。それが当たり前だったのは、コロナ前のこと、震災前のことで、もっと遡ればリーマンショック前ということになるでしょうが、これまで当たり前に通勤していた職場がなくなるというのは、銀行の合併による支店併合でも、よく見られることでした。
支店の併合によって、2つ、3つの支店が1つになりました。これによって支店長が支店の数だけ減りました。それによって職場がなくなった支店長は本社に呼び戻されます。それまでなら、新たな支店ができたときの予備軍として待機することになるのですが、支店が減っていく段階では、戻る先がない状態になります。そこで、待機部署が設けられ、銀行によって名称は異なるものも、一般には“部長部”と呼ばれました。
支店長は本社では部長に相当する役職です。部長だけが属している部署なので“部長部”ということですが、支店が新設されることがない状況では閑職であり、できることなら「自分から辞める」と言ってほしい、なくてもよい部署とされました。
私が知っていた支店長が部長部に転任(?)になり、もっと上層部の人を、たまたま知っていたことから部長部を訪ねる機会がありました。訪ねてみて驚いたのは電話もなくて、仕事というと銀行に緊急事態があったときに(火災や巨大地震など)、重要書類(と称する古い資料)を持ち出すために、ずっと室内に控えている役割を命じられていました。
どう考えても嫌がらせそのもので、そんな扱いに耐えられないからと自主退職を言い出すまでの居場所でしかありません。再就職先を探そうにも、転職希望先から「どんな仕事ができますか」と聞かれても、“管理職”としか答えられないようでは雇ってくれる会社もありません。
職場があってこその役職ですが、これからの時代は支店がなくてもATMがあればよい、ATMどころかスマホ決済だけでよいという時代には、管理職の存在価値は、ますます弱まっていきます。それなのに、まだ時代の変化に対応できずに、次を期待して待ち続ける人がいるのも事実です。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)