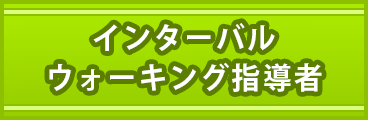集中することが究極な状態まで高まると、瞑想のような感覚になることは、書く瞑想として写経について前々回(正念16)触れました。
「書く瞑想」といっても、それは写経の代わりとして浄土真宗の宗祖の親鸞聖人が書かれた「正信念仏偈」(正念17に全文を紹介)を写すこともあるのですが、それ以前に書くことを仕事にしてきた中で感じてきたことです。
瞑想と似た感覚にならないと、世の中に伝わり、心を揺り動かし、読んだ方々に影響を与えるような文章にならないことを、書き進めるたびに実感するようになりました。
書く瞑想の表現が正しいのか“考える瞑想”と言うべきか、これから書こうとすることを集中して組み立てていくことだけでも“雑念が消える”という状態は把握できていました。
その書く対象は、ゴーストライターとしての単行本の執筆で、それまでの公益団体の機関誌の原稿書きでは得られない感覚でした。単行本の原稿は400字詰め原稿用紙で300枚の分量です。
それだけの量であっても、自分の思い通りに書けるものなら、それほど集中しなくても書くことは可能です。大手出版社で15年間に150冊を書かせてもらいましたが、初めの3冊は著者(にあたる方)が話している内容を文字にして、読みやすいように修正することが役割だったので、機関誌と同じように、興奮状態をキープすることでも対応できました。
ところが、著者が話したことに既存の資料に加えて、そこにゴーストライター(私)の感覚も入れて作品として仕上げていくとなると、興奮状態では続くものではありません。
どれだけ著者に成り代わり、著者の感性を理解して、表現としてはオーバーかもしれないのですが、“憑依する”(魂が降りてきた)状態となって書くためには、書き出す前の混乱状態から集中することで雑念が消えて、呼吸が整い、内なる平穏が得られることが必要でした。
単行本1冊の原稿を書き上げるのに、当時は速書きでも5日はかかりました。内容によっては2週間以上もかかることもあり、執筆している時間は長く集中するために、さまざまな手段を使いました。
音楽をかけることもあれば無音状態にすることもあり、室内の温度と湿度の調整、空腹状態で続けるか途中で軽食(私の場合はカロリーメイト)を入れることもありました。
それも書く内容と自分の状態をマッチさせての結果ということで、どれだけ修行をしてきたか、という感覚でした。
今は頸椎の神経圧迫による手の痺れと目の状態があって、あまり書けなくなったのですが、時代の進歩のおかげで音声文字変換という方法が使えるようになりました。
しかし、これでは考える瞑想、書く瞑想と同じ結果を得ることは不可能なことで、次の瞑想の方法を考えなければならない時期になったようです。
〔小林正人〕