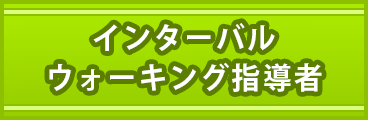医療の基本は検査をして、病名を特定して、それを改善することです。まずは検査をすることが重要ということを伝えるために、メディアでも「とにかく検査を受けよう」ということが強調されています。
検査をしないことには体調不良があったとしても、その原因を把握することはできません。また、体調不良がないとしても、変化に気づいていないだけで、検査をしないと本当のところはわからないというように言われます。
検査は人間ドックのように全身の状態を詳細に調べる方法であっても、診断は個別の状態が注目されます。全身を診ているから全身の関わりを把握して対処するための検査ではないのです。
身体は相関性があって、重要な器官はつながりをもって違いに影響を及ぼしあっています。特に有名なのは腸脳相関で、消化・吸収・排泄を行う腸と、刺激に反応して身体の働きを調整している脳神経は別々の元と考えられがちですが、実は密接に関係しています。
よく言われるのは、ストレスを感じると腹が痛くなり、腹の調子が悪いと不安が高まって脳の働きが低下するという単純なことではないのです。例を一つだけあげると、重要な神経伝達物質のセロトニンは脳神経で使われるものなのに、その90%ほどは腸内で合成されるという関係性になっています。
こういったことは、健康を全体的に考えていこうということで、統合医療という言葉を用いて説明されることがあります。ところが、日本では統合医療というと医療行為(主に西洋医学)に、それ以外のものを組み合わせた追加の代替医療が着目されることが多くなっていて、全体的に調整することが最重要で考えられていないところがあります。
では、どうすべきなのか、という話は次回に書かせてもらいます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕