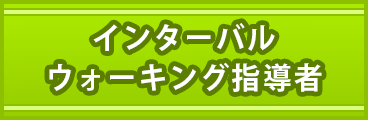厚生労働省から、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」が発表されました。
以下に、「健康づくりのための睡眠ガイド2023」の成人版の「睡眠の不調、睡眠休養感の低下をもたらす睡眠障害や更年期障害」を紹介します。
〔睡眠の不調、睡眠休養感の低下をもたらす睡眠障害や更年期障害〕
睡眠の不調(入眠困難や中途覚醒等)や睡眠休養感の低下が長く続く場合、背後に睡眠障害が潜んでいることがあります。不眠症はストレスを契機に発症することが多く、睡眠の不足とともに睡眠休養感の低下をもたらすことが報告されています。
閉塞性睡眠時無呼吸や周期性四肢運動障害は、日中の眠気・居眠りや睡眠休養感の低下以外の自覚症状に乏しいこともあります。これらの疾患は、いずれも50歳代以降に有病率が増加するため、注意が必要です。
また、労働世代の後半には更年期を迎えるため、さまざまな不調が生じやすくなります。更年期女性の4〜6割が睡眠の悩みを抱えており、仕事にも影響することが報告されています。
〔睡眠時間を確保する働き〕
労働者が適正な睡眠時間を確保する上で重要なのは、労働時間との関係です。勤務時間が長くなるほど、睡眠時間は短くなる傾向があるため、疲労が蓄積します。
労働時間と睡眠時間は関連が強く、米国民を対象とした1日の生活時間の大規模調査では、睡眠時間の短縮と最も強く関連していたのは勤務時間の長さで、次いで通勤時間を含む移動時間の長さでした。
我が国の労働時間と睡眠時間の関連についての調査研究でも、1日当たりの労働時間が7時間以上9時間未満の人を基準とした場合、男性の場合は睡眠時間が6時間未満になるリスクは、労働時間が9時間以上の人は2.76倍、11時間以上の人は8.62倍に著しく増加することが報告されています。
女性の場合も、労働時間が9時間以上の人は2.71倍、11時間以上の人は5.59倍に増加することが報告されています。
さらに時間外労働が1日5時間を超えると睡眠時間は著名に短くなるとの報告もあり、睡眠時間の確保のためには、長時間労働の是正等の労働時間の管理も重要です。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕