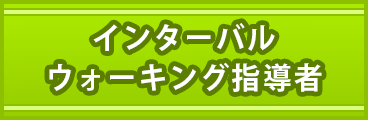健康に関わるチェックを実施してみて、同じ結果が出たとしても、それに対する意識が異なると、その後の継続と成果にも違いが出てきます。その例として話をさせてもらっているのは、食生活チェックをした人との面談での第一声です。
食生活チェックは、1週間に摂る食品の頻度の項目をチェックしてもらうもので、一般に実施されている1週間分のメニューと分量を書き出すものとは違っています。
メニューと量だけでは、何を増やせばよいか、何を減らせばよいかはわかりにくいところがありますが、食品の種類の場合は、チェックをしているうちに、これは食べ過ぎではないか、逆に少ないのではないか、ということに気づくことができます。
チェック項目にある食品を、まったく食べていない、1週間に1回ほどしか食べていないということになると、食べたほうがよい、1週間に何回かは食べたほうがいいということがわかってきます。
食生活チェックの結果を踏まえて、面談をするときには、いきなり指導はしません。「チェックをしてみて、どう感じましたか」と投げかけて、返ってきた返答の内容は7〜8割は指導しようと考えてきたことと同じです。
この段階で、指導は半分以上が終わっているようなもので、本人が気づいたことに対して、その裏付けとなること、どうして食べたほうがよいのか、どれくらいの頻度で食べればよいのか、これとは逆に減らす理由を説明するだけです。
自分で気づいたこと、変えようと思ったことを後押しするアドバイスは、継続効果が高くて、押しつけのように言われたこととは結果が違ってきます。
食生活の改善は、長い期間をかけて身につけてきたことを変えることになるので、心理的な抵抗感もあり、変えようと思っても、なかなか変えられない、いつの間にか戻ってしまったということにもなります。
それだけに、いかに自分で気づいてもらうか、気づいたことを続けられるように後押しするアドバイスができるかが重要になってくるのです。
〔健康ジャーナリスト/日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕