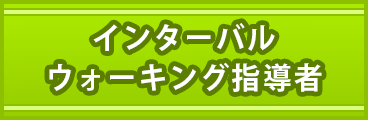活性酸素は、今では当たり前に認識されるようになっていますが、活性酸素が初めて一般向けにメディアで紹介されたときには、目に見えないものだけに、理解されない状態が続きました。目に見えないといえば酸素も見て確認することはできません。酸素が不足した状態で息苦しくなってから存在を認識するというくらいです。
活性酸素は、簡単に説明すると酸素からマイナス電子が1個だけ欠けているものです。酸素は通常はプラス電子が4個、マイナス電子が4個となってバランスが取れています。このうち1個のマイナス電子が欠けると不安定な状態になって、マイナス電子を他のところから持ってこようとします。
マイナス電子を持ってきたら、活性酸素は正常な酸素に戻ります。それなら問題はないのではないかと思われるかもしれませんが、問題はマイナス電子を奪われたほうで、人間の細胞がマイナス電子を奪われると細胞が破壊されます。人間の細胞はつながった状態で、マイナス電子は隣り合った細胞から次々と奪われていって、細胞はドミノ倒し状態で次々と破壊されていくことになります。
こういったことが起こるから、活性酸素は身体に多くに影響、大きな影響を与えると説明されているのですが、電子の移動は、それこそ目で見ることができないので、これを説明するのは大変な作業となります。そのため、イメージで、いかに伝えるかが重要で、それを伝える専門家のテクニック、話術が問われることになります。
日本の活性酸素研究の元祖とされるのは板倉弘重医学博士で、国立健康・栄養研究所の臨床栄養部長だったときに、赤ワインのポリフェノールの抗酸化作用を発表して注目されました。私は臨床栄養の仕事をしていたことから、板倉先生の研究は基礎段階から知っていました。板倉先生が退職後に日本臨床栄養学会の理事長を務められたときにも、ずっと付き合いを重ねて、東京にいたときには主治医をお願いしていました。
板倉先生の研究を一般向けの書籍として発行したのは、ごま書房とゴマブックスです。私が日本文芸家クラブの理事を務めていたときに、ごま書房の編集局長、ゴマブックスの社長と親しく付き合ってきた関係で、一般向けの広報に加わりました。
活性酸素についてテレビの健康番組で初めて紹介したのは久郷晴彦薬学博士でした。久郷先生は私の義父で、いかに一般向けにわかりやすく伝えるかを先生とテレビ関係者を交えて検討を重ねてきました。活性酸素そのものの研究よりも、目に見えないものを伝えることのほうが大変なくらいでしたが、その作業の繰り返しのおかげで、活性酸素に関する書籍を数多く手がけることができました。
そのときの経験を、活性酸素を多く発生させる紫外線が多い晴れの国の岡山で、さらに活性酸素を消去する作用がある抗酸化成分が多く含まれる果物の色素をフルーツ王国の岡山で活かしていこうと、講習の準備を始めているところです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)
投稿者「JMDS」のアーカイブ
胃で消化されたものを小腸で吸収するときには、ただ染み込むようにして血管まで運ばれていくわけではなくて、腸壁の細胞が栄養素を取り込んでいます。細胞に取り込まれたエネルギー源のブドウ糖と脂肪酸は、細胞の中でエネルギー化されるというイメージがあるかと思います。エネルギー化はされているのですが、エネルギー源を使って、細胞の中で作り出されたエネルギーを使って細胞は、それぞれの働きをしています。
腸壁の細胞はブドウ糖と脂肪酸を次の細胞へと送っていって、毛細血管に届ける働きをしています。この働きがスムーズに進むためには、腸壁の細胞の中で多くのエネルギーが作り出される必要があります。
大きなエネルギーを発生させるには、エネルギー量が多い脂肪酸を細胞のミトコンドリアに効率よく取り込む必要があり、脂肪酸と結合して取り込む働きをしているのは代謝促進成分のL‐カルニチンです。L‐カルニチンは肝臓と腎臓で合成されていますが、合成のピークは20代前半で、年齢を重ねるほど代謝が低下していくのはL‐カルニチンの減少が関係しています。L‐カルニチンは以前は医薬品の成分であったのが、今では食品成分として摂ることができます。
腸壁の細胞には酵素があって、それぞれの細胞の生化学反応は酵素によって促進されています。酵素の働きは細胞が温まるほど高まっていくという特徴があります。ミトコンドリアの中で発生したエネルギーのうち、半分ほどは細胞を温めるために使われています。ということは、効果的に脂肪酸を取り込んで、多くのエネルギーが作り出されるほど細胞が温まり、酵素の働きも高まって、細胞の働きがよくなるということです。
エネルギー代謝を高めることは、腸の吸収を高めることにもつながるというわけです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)
文部科学省の『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』(2012年)によると、発達障害の可能性がある小中学生は6.5%と発表されています。これは知的発達に遅れはないものの学習面や行動面に著しい困難を示すと担任が回答した児童で、あくまでも担任の主観に基づく調査結果です。
また、調査によると、発達障害の可能性がある児童生徒のうち、校内委員会で特別な教育的支援が必要だと判断されたのは18.4%と5人に1人にも満たない状態です。しかも、発達障害の可能性のある児童生徒のうち38.6%が「いずれの支援も受けていない」という結果となっています。
早期発見が充分でないこともあり、実際には発達障害児の割合は10%に達していると推定されています。海外の複数の調査では発達障害児の割合は14〜19%にもなっています。
発達障害の男女差は、前記の文部科学省の調査では男女比は2.4:1の割合となっています。海外の調査では男女比は4:1とされるデータもあり、男性の発症が多いとされるアメリカでは4.5:1との報告があります。
国内の調査では男子が女子の2.4倍の発現率という結果から、発達障害児が10%と推定した場合には男子で発見されているのは14%、女子では5.8%となります。一般には発達障害の男女差は7:3で男子が多いと言われていますが、それと合致した結果となっています。
発達障害の名称は病名にも法律(発達障害者支援法)にも使われていて、機能障害であるかのように勘違いされることがあります。しかし、神経の発達が遅れがちであるために、得手・不得手の凸凹(でこぼこ)が環境や周囲の人との関わりのミスマッチを招き、対人関係やコミュニケーション、行動や感情のコントロールがうまくできずに、社会生活に困難が生じやすい状態を指しています。この理解から発達支援は始まります。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)
血流の低下は、認知症のリスクを高めます。血液中の中性脂肪が増えすぎる脂質異常症は、食事と運動の内容が関わるだけに、自分でリスクを抑えることも可能となっています。
血液検査を受けて、中性脂肪の検査数値が高いことが指摘されるような状態になっても、これといった自覚症状はみられません。しかし、中性脂肪値が高いまま長期間放置しておくと、血管の老化が進み、動脈硬化から心疾患、脳血管疾患へと進んでいくことになりかねません。
血液中に存在する脂質には、中性脂肪、コレステロール、リン脂質、遊離脂肪酸などの種類があります。このうちの中性脂肪は英語名のトリグリセリド(triglyceride)を訳したもので、酸性、中性、アルカリ性という分類の中性とは関係がありません。グリセリド(グリセロール)と呼ばれる脂質1個に、脂肪酸が3個結びついたものです。
中性脂肪は、エネルギーを体内に貯蔵するための形態であり、血液中を流れる脂肪や体脂肪の内臓脂肪と皮下脂肪もほとんどが中性脂肪となっています。食品に含まれる脂肪も中性脂肪となっています。
血液中の中性脂肪が過剰に増えた状態を高中性脂肪血症といい、中性脂肪とLDL(低比重リポ蛋白)のどちらか、あるいは両方が過剰に増えた状態、もしくはHDL(高比重リポ蛋白)が低い状態を合わせて脂質異常症といいます。
脂質異常症は、以前は高脂血症と呼ばれ、2007年に病名が変更となりました。リポ蛋白の中でも、HDLは多いほうが動脈硬化のリスクが低下するため、高脂血症という名前は状況に合わなくなり、日本動脈硬化学会によって脂質異常症と名づけられました。
それに伴って、検査基準の中から高コレステロール血症がはずされ、高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高中性脂肪血症の3つが、脂質異常症の診断基準となりました。
脂質は水には溶けにくく、血液は水成分であるために、親水性のよいタンパク質、リン脂質、コレステロールが結合したリポ蛋白の形で血液中を運ばれています。リポ蛋白は成分比重の違いから、カイロミクロン、超低比重リポ蛋白(VLDL)、低比重リポ蛋白(LDL)、高比重リポ蛋白(HDL)に分けられており、それぞれ体内での作用が異なっています。
このうち主に中性脂肪を運ぶ役割をしているのがカイロミクロンとVLDLで、コレステロールを運ぶのがLDLとHDLです。LDLが多くなると動脈硬化のリスクが高まることから一般には悪玉コレステロール、HDLが多くなると動脈硬化のリスクが下がることから善玉コレステロールと呼ばれています。
悪玉コレステロールが動脈硬化の要因となっていることを知ると、コレステロールは悪いものと考える人も出てきました。しかし、コレステロールは全身の細胞膜の材料であり、ホルモンの原料になり、脂肪を分解する胆汁酸の材料にもなります。コレステロールは体に必要で、決して悪いものではないことは知っておくべきです。
発達障害の学習障害は、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害と並ぶ三大発達障害とされています。自閉症スペクトラム障害と注意欠陥・多動性障害については、脳のセロトニン不足が影響していることは前に紹介しましたが、学習障害についてもセロトニン不足の影響が指摘されています。
セロトニンは脳内の神経伝達物質で、ドーパミン、アドレナリンを制御して精神を安定させる働きがあります。また、セロトニンには脳の扁桃体に働きかけて恐怖や不安といったストレスを軽減させる作用はあります。セロトニンが不足するとドーパミンとアドレナリンのコントロールが不安定になり、ストレスのコントロールができにくくなり、意欲や集中力がなくなる、気分が優れない、疲れやすい、眠れないといった状態が起こるようになります。
神経伝達は、一つの神経細胞から別の神経細胞に神経伝達物質を使って伝えられていきます。神経伝達物質が不足すると、それだけ情報の伝達が遅れることになります。正常な発達では前頭前野の神経伝達が成熟することで思考、学習、注意、意欲、創造などの精神機能の調整が行われています。
発達障害は神経伝達のネットワークの機能不全が指摘されますが、一般には電線のような働きをする神経の配線に異常があるように理解されることがあります。これもあるとしても、それに加えて神経伝達物質のセロトニンの不足から伝達がスムーズにいかないことも大きな理由と考えられています。
セロトニンは遺伝的な要素もあるものの、環境因子のほうが大きく、セロトニンの材料となる必須アミノ酸が不足することによって、脳内で減少していくことが知られています。
セロトニンが増えると興奮作用があるドーパミンとアドレナリンの働きが抑えられ、セロトニンが減るとドーパミンとアドレナリンの働きが高まるというバランスになっています。セロトニンが減っているために、興奮しやすくなり、それが学習障害にも影響を与えるという結果につながっているということです。
日本人の平均寿命が10年ぶりに縮んで、男性が81.47歳、女性が87.57歳になったと報道されたのは2022年7月29日のことでした。10年前というと東日本大震災の影響があった年で、今回の結果に影響したのは新型コロナウイルスです。
このデータは、厚生労働省の「令和3年簡易生命表の概要」によるものですが、簡易生命表というのは、1年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の人が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命によって表したものです。
一般に平均寿命と呼ばれているものは、0歳児の平均余命であって、例えば65歳の男性が、あと21.47年生きられるということではありません。平均余命は主な年齢ごとに計算されていて、65歳の項目を見ると19.85年となっています。計算上の余命とは1.62年と大きな差ではないようですが、あくまで経済や生活環境、衛生環境などの死亡に影響する状況が変わらないという前提での話であって、前提が崩れるようなことがあったら、この先の20年ほどの期間は保証されるわけではありません。
思ってもみないことが起こることは「万が一」と表現されますが、1万日は27年ちょっとの期間で、27年前の1995年に何があったのか、そのときから社会的に何が変化したのかを見ていくと、そろそろ万が一のことが起こってもおかしくないことがわかります。
1995年はバブル経済が崩壊した直後で、銀行が倒産する、不良債権が拡大する、地価と住宅価格が下落する、日本の格付けが低下する、雇用が抑制されるという万が一の出来事が続きました。団塊の世代(1947〜1949年生まれ)の子どもの団塊ジュニア(1971〜1974年生まれ)は、1995年には21〜24歳で、まさに就職をする年齢で就職先が崩壊するような厳しい世の中に放り込まれることになりました。
「実質給与が30年間も上がっていないのは日本だけ」と言われますが、その洗礼を受けたのも団塊ジュニアでした。団塊ジュニアは毎年200万人も生まれた世代で、その子ども世代も大きく増えることが期待されました。しかし、生活が苦しい中で結婚、出産、子育ては難しく、第三次出産ブームは起こりませんでした。
この世代が新たな時代の担い手になることが期待されていたものの、それは儚い希望で終わり、日本の競争力を大きく低下させる結果となっています。国の成長を支えるのも介護社会を支えるのも人材ですが、その人材が不足している時代では、これまでの常識をスケール(物差し)にしていたのでは、さらに崩壊に向かって進みかねないという恐怖心があります。
これを克服していくために何をしなければならないのか、そのことを真剣に考え、次の世界に向かってスタートを切らなければならないタイミングに足を踏み入れています。それを認識して、意識を変えることから、次の世代への案内役の務めが始まるのではないかと考えています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)
1日に食べている量を100kcal単位で確認する方法を前回は紹介しましたが、摂取エネルギー量が1日の必要なエネルギー量と合っていればよいというわけではありません。栄養バランスが取れていなければ、全体量が合致していても喜ぶわけにはいきません。
栄養バランスについては、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」(2020年版)でエネルギー源の割合として示されています。エネルギー源というのは、食品の中に含まれているエネルギーとなる糖質、脂質、たんぱく質を指しています。これ以外のもの(ビタミンやミネラル、食物繊維など)はエネルギーとはなりません。
「日本人の食事摂取基準」のエネルギー産生栄養素バランスによると、炭水化物50〜60%、脂質20〜30%、たんぱく質13〜20%となっています。炭水化物は糖質と食物繊維を合わせたもので、食物繊維にもエネルギーは含まれているものの消化も吸収もされないので、炭水化物と書かれていても摂取エネルギー量としては糖質と同じと考えることができます。
主食(ご飯、パン、麺類など)は糖質が多く食品ではあるものの、たんぱく質も脂質も含まれています。ご飯の場合には55%ほどが糖質となっています。エネルギー源の割合ではなくて、食品としての摂取エネルギーを100kcal単位で考えてバランスを取るようにすると、例えば1日に1600kcalを摂取する場合には、主食が800kcal、たんぱく源の主菜(肉、魚、卵、大豆製品)が400kcal、副菜の野菜が100kcal、牛乳が100kcal、果物が100kcal、そして油が100kcalとなります。
副菜は野菜の他に汁物となります。小鉢やサラダの1食分が25kcalとして、1日に4つを摂るようにします。油は意識して使わなくても調理したものや加工食品に含まれています。
1600〜2000kcalまでは主菜の400kcal、副菜の100kcal、牛乳の100kcal、果物の100kcal、油の100kcalは同じにして、主食だけで調整します。つまり、2000kcalでは主食は1200kcalとなります。
これらを目で見てわかるようにするために、主食は黄色、主菜は赤色、副菜は緑色に色分けして、1枚が100kcalの紙を摂取エネルギー量の分を用意して、1日のメニューを考えるようにしています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)
健康食品の名称は法律に違反しなければ、どのような名称にしてもよいわけです。以前、商品名に効能効果を掲げたものがありました。それ以前の規制のマニュアル(無承認無許可医薬品監視指導マニュアル)には広告やチラシ、パッケージなどの表記の規制については書かれていたのですが、これを契機に商品名も規制する文言が加わった経緯があります。
商品名に優位さを示す言葉が使われると、なんだか効果がありそうに思えるところがあります。それほど優れていないだろうという商品にスーパー、ゴールド、スペシャル、デラックスなどという言葉が使われている例もあって、怪しさを感じることがあります。
商品のシリーズに共通している固有名詞は隠して話を進めますが、レギュラー商品の○○より優れたスーパー○○という商品が発売されて、これはよくある命名法であるので、特には気にしていませんでした。ところが、スーパーデラックス○○、スペシャルスーパーデラックス○○、スペシャルスーパーデラックス○○ゴールド、スペシャルスーパーデラックス○○プレミアムゴールドと相次いで発売されました。
何が違うのかというと、原材料に使われている素材の数が、どんどんとプラスされて、最後は48種類もの抗酸化物質が使われていました。抗酸化物質は活性酸素を消去する性質があるもので、その多くは植物に含まれていて、色素の中に多く含まれています。
抗酸化力が強いものを使えばよいのか、それとも抗酸化成分は効果的に働く臓器や器官などが異なるので数多くの種類を使って多くの臓器などの働きを高めればよいのかということについては、いまだに結論が出ていないところですが、次々と抗酸化成分の数を増やして、その代わりに各素材の量を減らしていったのは、後者の考えがあってのことだということでした。
筋肉には種類があって、筋肉によってエネルギー源が異なるというのはメディカルダイエット講習の基本的なこととして伝えています。その筋肉は色で分けると白筋と赤筋、動く速度で分けると速筋と遅筋になります。白筋が早く動いて習慣的に大きな力が出る速筋で、赤筋が強い力はないものの長く動き続けられる遅筋となっています。酸素の使用については、無酸素運動に向くのは白筋で、有酸素運動に向くのは赤筋です。
筋力は筋収縮力、筋持久力、筋代謝力に分けられていて、白筋は収縮力が強く、赤筋は持久力が強いことになります。筋代謝力のほうは、どれだけエネルギー代謝をして、エネルギー源を効果的に使えるかという能力で、一般には赤筋の特徴を示すときに使われます。
というのは、エネルギー代謝によって大きな力を発揮できるのはエネルギー量が大きな脂肪酸で、運動によって作り出されるエネルギー量も大きくなっています。脂肪酸は1gあたり約9kcalと、ブドウ糖の約4kcalに対して2倍以上になっています。
講習テキストでも、この範囲で違いについて説明しているのですが、激しい運動をしている人からは、別の筋肉の名前があげられることがあります。それはアネロビック筋とエアロビック筋です。トライアスロンのように激しい運動をする人たちから、よく出てくる分類ですが、アネロビック筋は白筋、エアロビック筋は赤筋のことです。
わざわざアネロビック筋とエアロビック筋という名称を使っているのは、どちらの筋肉が優れているというのではなくて、両方の筋肉を有効に働かせることが重要という考えからのようですが、それは特別なことではなくて、今では当たり前のことになっています。
アネロビック筋が激しく動くと乳酸や老廃物質が多く作られるので、エアロビック筋によって乳酸も老廃物質も分解しようということで、確かに無酸素運動のあとに有酸素運動をすると疲労物質である乳酸を、エネルギー源として使って、より多くのエネルギーが作り出されて、激しい運動にも耐えられるようになるという説明がされています。
激しい筋肉運動をしたあとには、ウォーキングやバランスボールを使ったバウンド運動といった有酸素運動をするのは、赤筋と白筋の特徴に合わせた方法となっています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)
発達障害児の支援は、発達障害を理解することから始まります。発達障害は生まれつき脳の発達が通常と違っているために、身体や学習、言語、行動において幼児のうちから症状が現れ、通常の育児ではうまくいかない状態を指しています。幼いときには本人は特に意識することはないかもしれませんが、成長するにつれて自分自身のもつ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあります。
発達障害は通常は生涯にわたって継続するものですが、その特性を本人や家族、周囲の人がよく理解し、その人に合ったやり方で日常的な暮らしや学校、職場での過ごし方を工夫することができれば、持っている本来の力が、しっかりと活かされるようになります。
発達障害は、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」(第2条)と定義されています。
発達障害は、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3つに大きく分類されています。このほかにトゥレット症候群、チック障害、吃音(症)なども発達障害に含まれます。
発達障害の特徴が重なり合っている場合も多く、どのタイプにあたるのか発達障害の種類を明確に分けて診断するのは難しいとされています。年齢や環境によって目立つ特性が違うことから、診断された時期によって診断名が異なる場合もあります。
これらは、生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通しています。同じ人に、いくつかのタイプの発達障害があることも珍しくはなくて、そのため同じ障害がある人同士でも、まったく似ていないように見えることがあります。個人差が非常に大きいという点も発達障害の特徴といえます。
また、複数の状態が重なり合って現れることもあり、そのために発達障害の種類を明確に分けて診断することは難しく、このことが早期発見が遅れることにもつながっています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)