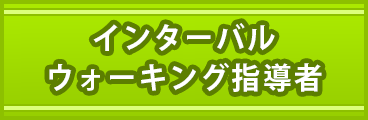発達障害者は、発達障害があるだけでなく、社会障壁があることによって困難さを抱えている人を指しています。これは発達障害者支援法によって定義されていることです。
発達障害の障壁は、今現在の障壁であって、テクノロジーの進歩によって克服できると信じて支援することもあります。完全に信じて、と言えないのは、それぞれの特性とテクノロジーがマッチするかわからないところがあるからです。
自分のことを書くと、3歳で親元を離れて暮らすことになった母の実家の寺では、子ども向けの本も少なく、仕方なしに仏教の書籍や、ときには経典を本の代わりに読んでいました。
内容など理解しようもなく、祖父のお経を楽譜のように感じて、文字を覚えていきました。
難しい漢字も読めるのに、他人にわかるように文字が書けないというのが祖父母や叔母などの評価で、今にして思えば、未就学の子どもが漢字、それも経文を書くことは不可能なことだったはずです。
しかし、同居する家族の本気か嘘かわからない「字が汚い」という評価は、住職は無理だとの思いをしていました。お寺の人は誰もが字が綺麗と思い込んでいたことがあります。
幼いときには、という思いだったのに、小学校でも中学校でも高校でも、なんとか読めるけれど、どんなにお世辞を言っても、上手だ、個性的だと言えない状態でした。
大学を卒業して、社会人になったときにワードプロセッサーが登場して、大型で手が届くものではなかったのですが、何を間違えたのか、大手出版社でゴーストライターを務めることになり、「文章はうまいが読みにくい」との評価をひっくり返すことになりました。
シリーズの数冊の原稿を書いて終わりかと思っていたのに、いきなり小型(といっても今の大型デスクトップパソコン並みの大きさ)のワードプロセッサーが家に届けられました。
これで清書して提出しろということでしたが、そのまま打ち込んで文章にしたらカッコいいだろうとの考えで、ブラインドタッチの意味もわからないときから、オリジナル(?)の打ち方で文章を作っていきました。
それが健康関連の雑誌などで役立つことになって、字が下手でも食べていけるようになりました。
ペンで書かなくなったことで、時が経つにつれて文字のレベルが年齢とは逆戻りしていくという、困った経験もしました。
今でも公式文書や申込書が書き直しを求められるという状況で、年齢もあって、ますますパソコンの文字変換ソフトがなければ生きていけないという状態になっています。
手の代わりの生活ツールとフィットすることができれば、書字障害があっても生き残れるというのが、デジタル時代の利点だと力説することができるようになりました。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)