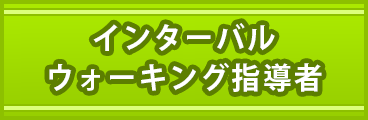高齢者の定義は時代や地域によって異なり、世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。日本では行政上の目的によって異なるものの、「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年)によって定義された65歳以上を高齢者とすることが一般に認識されています。
高齢者のうち65〜74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と分けて定義されています。
この分類が始まったときから前期高齢者のほうが後期高齢者よりも多かったのですが、2018年(平成30年)には、後期高齢者(約1770万人)が初めて前期高齢者(約1764万人)を上回り、それ以降は後期高齢者が増え続けています。
2025年には団塊の世代(1947〜1949年生まれ)の約800万人が、すべて後期高齢者となり、その数は1937万人(総人口の15.5%)と推計されています。
2025年は以前から懸念されてきた我が国の社会構造の大きな分岐点であり、全人口の30%以上が高齢者(65歳以上)、団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者となり、これまでとは異なる厳しい対策が必要になることから「2025年問題」と呼ばれています。
2025年には、これまで急激に延びていた高齢者の人口増は緩やかになっていくものの、生産年齢人口(20〜64歳)が大きく下がっていくことから生産能力も今以上に大きく低下していきます。
2040年には高齢化率は35.3%にも高まり、生産年齢人口は約1000万人の減少になると予測されています。これは危機感を持って「2040年問題」と呼ばれています。
日本の少子高齢化の特徴的な問題は、子どもが減って高齢者が増えることだけではなく、全体の人口が大きく減っていくために、高齢者が産業を支える立場となり、年々その重要性が高まっていくことにあります。
すでに人口は2008年には1億2808万人とピークに達しており、それ以降は減少に転じて、2050年(25年後)には1億人を下回り、2100年には5000万人を下回ると予測されています。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕