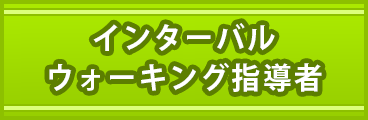発達障害児の食の困難さを初めて知ったのは、小児肥満の研究に参加したときのことでした。発達障害が医学界で知られるようになったのは1970年ころからですが、広く知られるようになったのは1993年のことでした。そのときには通常学級に通う子どものうち発達障害と判断されたのは1万2000人ほどでしたが、2021年には16万人を超えていて、調査のたびに増えています。
小児肥満の研究を始めたのは1990年のことで、研究の概要書には“発達障害”という文字は書かれていなくて、子どもを対象とした指導も通常の成長と肥満の関係性が重視されていました。成長過程の子どもは体脂肪を減らすことよりも、身長を伸ばし、筋肉を増やして代謝を高めることが重視されていました。
そのために栄養摂取と運動が重要というのは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対応の生活指導(特定健診・特定保健指導)でも重視されていますが、成人の場合は飲食による摂取エネルギー量を減らし、運動による消費エネルギー量を増やすことで対応することが可能です。
ところが、成長期の子どもの場合には、食事量を減らさずに、運動も負担をかけることがないようにしながら肥満を解消していくという難しいアプローチが必要になります。
それを可能にしたのがメディカルダイエットでしたが、指導どおりに実施してもらえれば成果が得られる方法であったのに、指導どおりにいかない子どもが5人に1人くらいの割合でいました。その原因を追求する調査で、好き嫌いを超えた極端な偏食があって、どんなに保護者が食べさせようとしても食べられないことがあることがわかりました。
今では発達障害による食の困難さ、五感(味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚)の感覚過敏によって好きなものであっても食べられないことは明らかにされていますが、当時は、その原因がわからず、なんとか対応するために専門家を紹介してもらい、脳科学を学びました。
食べにくいもの、食べられないものがあっても、他の食品で同じ栄養素を摂取する方法は当時からありました。食べられれば問題が解決されるということではなく、困難さを抱えながら、それを保護者に気づかれないようにして食べているという子どもなりの「偽る脳力」を使って辛い思いをして食べている例も少なくありません。
そのことがわからずに食品を変え、調理法を変えるという従来の対応は、当時から今のように発達障害の特性がわかるようになってきても続いています。脳科学に基づいた子どもの心理を理解した上で、どのような「偽る脳力」を使っているのか、そのことを理解することが重要です。
そこに着目して、ずっと研究し続けてきたのが“発達栄養”という独自のジャンルで、偽ることがなく食べてもらえるように発達障害と栄養摂取の理解を進めていくことが自分の務めだと強く認識しています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕