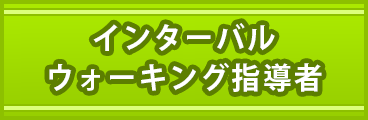寺が災害から復興するための作業場になったということを前回書きましたが、さらに親の作業を手伝う子どもたちの集いの場にもなっていました。
漁師町であり、男手が漁に出ているときは女手が家の一切を担っているような地域であったので、寺で紙風船を作るために女性陣が集まるということは子どもも一緒にくるのは当たり前で、赤ちゃんから入学前の子どもまで一緒にいるのは当然のことでした。
災害があったのは夏休みの期間だったので、上は高校生まで出入りしていました。年上の者が下の者の世話をするのも家庭内の延長というよりも、地域で子どもの世話をするのも当たり前の感覚で、地域のコミュニティの縮小版が寺の中に詰め込まれている感じでした。
だから、おやつも共有されていて、ここでも分け隔てなく、我慢することなく皆で食べるのは普通のことでした。
同じ場所で同じ時間を過ごし、宿題だけでなく生活のマナーまで知りたいことは教えてもらえて、多少のギクシャクはあったとしても同じものを食べることで気持ちが一緒になるという、寺子屋の原点のような状態でした。そこで覚えたことは、寺が集会場や作業場の役割を終えたあとも続いていました。
寺に行けばよいことがあるということを子どもたちが覚えたのは、やはり甘いものの存在でした。昭和30年代は高度成長期が始まっていたとはいえ、まだまだ貧しいところがあり、町でお菓子を売っているのは2店舗だけで、そこ以外でお菓子がたくさんあるのは寺という感じでした。
葬式や寺の儀式のときだけでなく、饅頭もあれば干菓子もある、おやつといえば“3時”だけでなく10時も当たり前で、お茶が出るときには“お茶菓子”がつくのは当たり前でした。
そういう環境だったので、寺に集まっていた子どもたちだけでなく、その友達も何かと理由をつけては、やってきていました。
サザエが採れたので持ってくる、檀家の用事を子どもが引き受けてやってくる、回覧板を持ってくる、郵便配達の代わりに持ってくるということから、寺で寂しく過ごしている私と遊んであげようという理由をつけて、とにかく次から次へと誰から来るという状態でした。
何か用事があってきた子どもには、お茶菓子が出る、帰りには甘いものを持たせるというのが常態化していたので、寺を離れて父の勤務地に戻ったときに、他の家を訪ねても甘いものが出るのは当たり前ではないことに初めて気づきました。
父の勤務地は農村地だったので、訪ねた先でもらって食べたのは、味噌をつけたキュウリということもあり、売るわけにはいかないものを子どもにあげるというのは、寺も一緒だということも感じた機会でした。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕