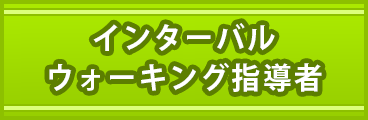発達障害は子どものときに発見され、大人になっても改善するものではない、と言われます。一般の認識の中には、発達障害は子どもに特有のもので、成長するにつれて改善していくものと捉えている人も少なくないのですが、治らないというのが医学的な見解で、私たちとしては抵抗感があるものの、“障害”という言葉が使われている所以ともなっています。大人になると社会との付き合い方が徐々に身についてきて、対応力が高まることで発達障害の状態が見えにくくなるだけだ、とも説明されています。
それなのに、子どものときには発達障害と診断されずに、大人になってから発達障害と診断されることもあります。これは、どういうことなのかというと、まずは見逃しがあげられます。発達障害者支援法には、地方公共団体の責務として“早期発見”“早期支援”が明記されています。早期発見がされていれば、早期に支援をして発達障害の程度を抑えることができるということですが、早期発見が充分にできるだけの体制が整えられていないと見逃されたまま大人になる人も増えてきて、それが大人になって厳しい社会対応をしなければならない場面に遭遇したときに、発達障害の状態が現れてしまうということになります。
早期発見は重要だということを言うのは簡単ですが、早期支援の仕組みと対応できるだけの施設、マンパワーがないことには困るようなことを言われて、早期発見をすることで文句を言われることにもなりかねないということです。
発達障害を見逃した医療関係者や学校関係者の責任だけでなく、もう一つ問われているのが親の責任です。発達障害であることがわかると、子どもが差別されるだけではなく、進学でも就職でも不利になるのではないかという思いから、隠してしまうことがあります。それに加えて、子どもを発達障害にしたと非難されることを恐れているということもあります。そんな思いがあると、医療機関に行くべきタイミングで行かないばかりか、周囲に行くようにすすめられても行かないということにもなります。
そんなことが起こるのも、発達障害が社会に正しく理解されていないからで、正しく理解されるための活動も、発達障害児を支援する人を支援することを打ち出している立場の人たちの役割だと認識しています。