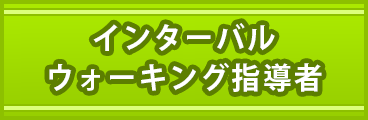「必要なものさえあれば生きていける」という感覚がある一方で、「便利なものがなくなる寂しさ」という感覚があるのは普通のことなのでしょうが、私の場合は「必要なものがなくても生きていける」「便利なものはなくなるのが当たり前」という感覚があり、これは子どものときから今までの生活環境が影響しているようです。
情報収集、情報分析、情報発信を生業にしてきた身からすると、情報が山のようにある書店は、ありがたい存在でした。物心がついてから小学3年生になるまでに住んだ3か所には書店はなく、3年生のときに洋品店に雑誌が少し並ぶという程度でした。
今のようにコンビニに雑誌や書籍が置かれている時代に、行動範囲に紙媒体の情報が手に入らないという地域はほとんどなくなったと思いますが、書籍や雑誌に触れる機会は都市部に出たときくらいでした。
情報格差という言葉を知らないときから、都市部で暮らしている従兄弟(父方も母方も)の家に行くと書籍や雑誌があり、その中に書かれている事柄が話題にのぼると“何を話しているのかわからない”という疎外感がありました。
父親は警察官で、家には仕事関係だけでなく辞書や百科事典もあったのですが、幼い時だったので、読めるような状態ではありませんでした。3歳になる前に親元を離れて母親の実家の寺院で暮らした3年ほどの間には、書籍といえば仏教関係のもので、子どもが読める絵本も1種類だけだったので情報はないに等しい状態でした。
4年生のときに1年だけ暮らした都市部には書店が2軒あり、歩いて20分以上はかかるのに、時間さえあれば通っていました。そこには1年間だけしかいなくて、その後の3年半を暮らした町には書店はなくて、新刊は手に入らないので、父親の百科事典(全20冊以上の全集)を愛読書としていました。
学校の教科書に載っていないことが多く書かれていたので、全ページを端から読んでは、疑問などがあったら父親と母親に質問をするという日々だったのを覚えています。忙しい父母にしたら、やかましい存在だったのでしょうが、「好奇心を途絶えさせてはいけない」という父母の考えのおかげで、百科事典にも書かれていないことを知ることができました。
百科事典と父母の知識がなかったら、情報を得る便利なものがなくなった不安感に押しつぶされていたのではないかと今にして感じているところです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕