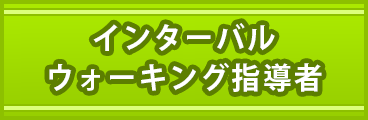日本の栄養学は、明治時代から始まっていたものの、国民の健康づくりの基本として据えられたのは終戦後のことです。それは終戦から2年後の1947年(昭和22年)からとされています。
戦後の日本は極端な食糧難の状態でした。その原因としては戦争の徴用と軍需産業への動員のために農村労働力が減少したこと、農機具や肥料が欠乏状態だったことに加えて、異常気象によって米の生産量が平年の半分以下という不作であったことがあげられています。
このような時代背景であったことから、日本の栄養学は栄養不足による健康状態の悪化を改善することから始まりました。このときの栄養学は国民全体の栄養状態を良くすることが重視されたことから、のちに「公衆栄養学」と呼ばれました。
その当時の平均寿命をみてみると、1947年には男性が50.06歳、女性が53.96歳でした。現在(2024年)では男性が81.09歳、女性が87.14歳となっているので、男性は31.03年、女性は33.18年も平均寿命が延びています。
これには栄養摂取の向上が大きな影響を与えました。1946年(昭和21年)の摂取エネルギー量(男女平均)は1903kcalでしたが、1955年(昭和30年)には2104kcalとなり、翌年に発表された『経済白書』では、戦前の最高水準を上回る回復を遂げたことから、「もはや戦後ではない」と宣言されました。
1975年(昭和50年)には摂取エネルギー量は2226kcalと、現在と比較しても最高レベルに達しました。その一方で、過剰摂取による生活習慣病の患者は増え続け、食事の関心も飽食の時代に対応する内容へと変化しました。
ただ食べ過ぎを抑えることだけでなく、性別、年齢、活動などに合わせて、個別に対応することが重視されるようになりました。2008年にはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に対応する特定健診・特定保健指導が始まりました。この個人対応の栄養学は「人間栄養学」と呼ばれました。
高齢化が進むにつれて、生活習慣病予防だけでなく、足腰の健康の増進も重視されて、フレイル予防のための栄養学も注目されるようになりました。フレイルは健康と要介護状態の中間の状態を指していて、予備能力低下によって身体機能障害に陥りやすい状態で、2014年に日本老年医学会から学術用語として提唱されました。
これに対応する予防対策としての栄養学は「予防栄養学」と呼ばれ、身体の状態と疾患の悪化をともに予防するということで、これは私が学んできた“臨床栄養”の範疇といえます。
ここまでは医師が大学で学ぶことができる内容ですが、今ではより健康になり、身体機能と脳機能を含めた機能向上を目指した栄養学が重視されるようになりました。
これは「発達栄養学」と呼ばれ、性別、年齢、活動量(運動、日常活動)だけでなく、個々の身体の成長や発達に応じた能力を発揮させる栄養学となっています。
発達栄養学については次回(日々修行89)に詳しく説明します。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕