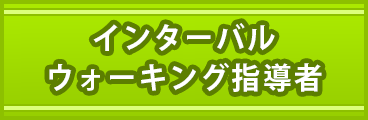発達栄養学は、発達障害児のための栄養摂取として研究が始まりました。発達障害児であろうと、定型発達(発達障害を伴わない)の子どもであろうと、それ以外の人であろうと、栄養学の基本中の基本が変わることはありません。
食べたものは咀嚼によって食道に送られ、胃で消化され、小腸で吸収され、血液中に入ってからは循環して、内臓や器官で代謝して、大腸を通じて排出されるという一連の流れに違いはありません。
この一連の流れの始まりは食べることで、必要なものを食べれば流れが始まるというように考えられるところですが、発達障害がある子どもは、その始まりの食べることにも高いハードルがあります。
発達障害の特性の一つに感覚過敏があります。感覚過敏によって五感(味覚、視覚、嗅覚、聴覚、触覚)が過敏に反応すると、食べられないものが多く出てきます。その食べられないものというのは好き嫌いの範疇を超えていて、味が問題なら味を誤魔化せばよいということではありません。
食べられないものは絶対に食べられないので、無理に食べさせたり、騙して食べさせるという手段は通じません。ところが、栄養摂取を中心に考えるあまりに、無理強いや騙すような摂取法をすすめる専門家も少なくありません。特に、子どもに対しては、そのような対応がされることが多くなっています。
そのようなことをしたために、望まないことをした人のことを嫌いになり、その人が作ったものを食べられなくなるということも起こります。これは栄養学というよりも、心理学など他の分野での対応にもなります。
それでも必要な栄養は摂らなければならないので、食べられるもの、食べられる調理などによって摂取できるようにすることがあります。
例えば、野菜がまったく食べられないという子どもにも、もちろんビタミンとミネラルは必要です。そのビタミンとミネラルを摂ってもらうためには、食べられるものの中から探すしかありません。それがサプリメントやジュース、栄養補助食品や乳児向けの粉ミルクになることもあります。
そのような手段まで用いた栄養摂取を指導することも、発達栄養学には必要とされるものの、心身が拒否をしている食べ物を摂取することによって、食べたものが通常の想定通りに吸収されるのか、体内で使われるのか、そこまで考えて摂取法や摂取量を考えるのが発達栄養学に求められることです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)