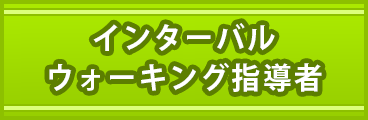大人になって発達障害が起こるのは、子どものときに発見できなかったことが大きな原因だと考えられています。確かに、子どものときに注意して観察をしていれば早期に発見できて、早期に支援を始めることで改善させることができます。親は気づいていたのに、周囲を気づかって専門医にみせなかったということを聞くと、大人になってから発見されただけで、子どものときに特性がなかったわけではないという考えも理解できることです。
こういったことが言えるのも、発達障害は脳の発達のズレによって起こるもので、年齢を重ねて治るものではないからです。むしろ、年齢を重ねることで状態が悪くなることもあります。子どものときには家族や学校のサポートがあり、その環境の中で基本的に暮らしているので、生きにくさを感じていたとしても障害と本人や家族が感じるほど、診断する医師が感じるほどのことではなかった、ということもあります。
また、子どものときには負担と責任があったとしても限定的で、そのことが大きな負担にならなかったのに、大人になってからは負担と責任が大きなプレッシャーとなっていくことにもなります。仕事で責任を持たされるということだけでなく、結婚して、子どもができて、子どもに関わる責任もかかってくるということになってきます。そのために、対応能力の限界を超えてしまい、これが発達障害として現れるようになります。
子どものときには現れにくく、大人になってから認められるのは発達障害の中でも注意欠如・多動性障害での報告が増えていますが、あとになって子供のときにグレーゾーンだったと言われることもあります。グレーゾーンは症状が見られても診断基準を満たしていないために発達障害とされなかったものです。グレーゾーンという言葉は正式な診断名ではなくて、「注意欠如・多動性障害の傾向がある」といったように伝えられます。
生活習慣病の場合にはグレーゾーンというと、予備群という言葉で表される症状が軽い人を指していますが、発達障害の場合は症状が軽いとは限りません。その日の調子によって変動があって、①調子がよいときも悪いときも診断域にない、②調子が悪いときだけ診断域になる、③調子がよいときも悪いときも診断域にあるものの支援が必要な状態ではない、という3つに分けられています。
本来なら③の診断域にあっても発達支援が必要ではないとされている場合も、発達障害と同じ支援が受けられるようになってほしいところですが、支援施設の不足などによって、これは難しいことです。だから、日本メディカルダイエット支援機構の発達支援の取り組みは、施設ではなく家庭で親が対応できるように、教育と情報発信による支援から始めているのです。