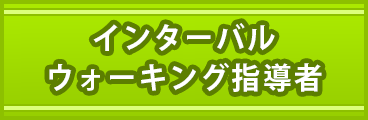幼いときに親元を離れて母の実家のお寺で過ごしていたときに、お寺にあった子ども向けの仏教の冊子を読んで、苦しい状況を乗り越えないと彼岸には行けないということを、ぼんやりと感じていました。
親元に戻ったときには、「喉元過ぎれば熱さ忘れる」といった感覚で、特段の苦労を感じることもなく育った気がします。幼いときに感じていた彼岸も、大人になってからは“お”がつく季節のお彼岸となり、お参りに行く日、そういえばお寺にいたときには来客が多くて、お茶を淹れるだけでも忙しかったことを思い出すくらいになりました。
本当の意味の彼岸を感じるようになったのは、医療や健康、福祉に関わった仕事をしてきて、コロナ禍でやるべきこともできなくなったときに、自分の無力さに気づいたときでした。そのことを悔いるのではなく、苦しい状況を、ただ苦しいと感じることを煩悩(ぼんのう)として捉えて、その煩悩の流れを超えた先の彼方にある安らぎの涅槃の地に行くために何をすべきかを考えるようになりました。涅槃の地というのは、実際にあるわけではなくて、仏教では悟りの境地を表しています。
「喉元過ぎれば暑さ寒さも彼岸まで」という理解しにくい言葉を使ったのは、コロナ禍という誰も経験したことがない時代、再び同様の感染症が起こったときに対応できるのか不安で仕方がない時代に、先々には彼岸にたとえられるような悟った人には過ごしやすいと感じられる場所があるということを示したかったからです。
コロナ禍で大被害を受けた人からは、このまま仕事を続けても「幸せになれるのか」という言葉を何度も聞きました。そのときに話したのは、「幸せは感じるもの」という当たり前のことでした。その具体的な話の内容については次回に続きます。