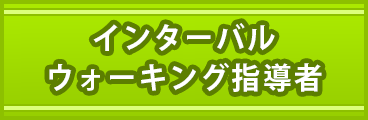今では発達障害によって偏食が起こり、中には極端な偏食もあって、通常の方法では対応できないことも随分と知られてきました。
すべての子どものうち発達障害児が10人に1人は存在することが知られるようになってから、極端な偏食についても理解が進み、無理に食べさせようとすると悪影響を与えて、かえって食べられなくなることも理解されるようになってきました。
発達障害は生涯に渡って特性が続くことから、対応を誤って食べにくいものを食べられないものにすることがないようにしなければならないのですが、なんとか栄養を摂取させて成長させようと思うあまりに、生涯に渡って食べられない状況を作り出すことにもなりかねません。
発達障害児の極端な偏食も、成長すれば治ってくると考えられることもあります。実際に年齢を重ねるにつれて野菜が食べられるようになった、苦手な肉類がなくなったという話は聞きます。そのことから、「今は心配をしないで食べられるものだけを与えておけばよい」ということを話す方もいます。それが発達障害児を育てた保護者の言葉であると、真実味をもって感じるかもしれません。
しかし、成長をして食べられるようになったのは、発達障害児の極端な偏食ではなくて、単なる好き嫌いであったり、子どもが嫌うからといって親などが食べさせてこなかったために慣れていないだけということも少なくないのです。
それを極端な偏食を克服したといって、他の保護者に押しつけるようなことも、よく見られることです。
まだ発達障害という言葉もない時代のことですが、小児肥満の改善のために国立病院のチームに加わったときのこと(国立病院の管理栄養士のOBが代表の研究所に所属してことから参加)、栄養指導をしても成果が現れにくい子どもが10人に1人ほどいて、しかも男女比は、対象を変えて何度も調査しても男児7対女児3くらいの割合になっていました。
今にして考えると、発達障害の割合と同じなのですが、そのときは好き嫌いの範疇の偏食と栄養の専門家も考えるような状況でした。
発達障害が医学的に明らかになり、食事の特性もわかるようになってきましたが、栄養面での改善の手立ては歩みが鈍くて、いまだに私たちが発達障害を知らない状況の中で手探りで対応してきたのと同じような状況が続いていると感じています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕