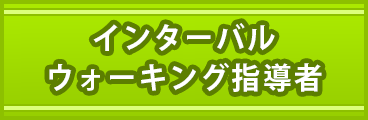「認知症のよいところ」という話をする専門家がいます。医薬品の有効性の調査をするときには、本物の医薬品成分が含まれたものを使ってもらうグループと、本物の成分が含まれていないプラセボ(偽薬)を使ってもらうグループとに分けています。偽物なら効果がないのは当たり前と考えるかもしれないのですが、使っている本人(治験者)には本物か偽物かを伝えていないのですが、本物と思って使っていると、有効成分が含まれていないのに効果が得られることがあります。この分を本物の結果から差し引いたのが、その医薬品の有効率ということになります。
このプラセボ効果を考えなくてよいのが動物試験で、医薬品を使っている意識がないので100%の結果を得ることができます。認知症の患者も同じことが考えられていて、正常な判断能力がないことがプラスに作用するという話です。認知症患者に対しては、正確な情報が伝えられないというのが医学者の感覚のようで、浜松医科大学とミシガン大学の研究グループが、かかりつけ医に対して患者を認知症と診断したときに、その情報をどのように伝えているかを調査しています。調査対象は都市部と僻地の各12名、合計24名の医師にインタビュー調査をしています。その結果、認知症の診断の告知の仕方に差があり、適切な伝え方がわからないと感じている場合がみられることが浮かび上がってきています。
認知症の病名の告知は、患者の家族に対しては必ず行われています。これは当然のことですが、患者本人への告知となると、①基本的に実施する医師、②実施しない医師、③必要ないと考えている医師に分かれます。認知症があることについては、①患者へ明示する場合、②湾曲的に伝える場合、③まったく伝えない場合がありました。伝えるにしても、通常の診断結果を話すのと同じようにはいかないようで、段階的に伝えていくようにする例が目立っています。また、認知症であること、その状態を患者本人に話してみても特段の効果があるわけではないことから、症状への対応方法について助言をする程度で終わる例もみられます。
認知症であっても、理解度には大きな差があり、どうせわからないだろうという考えで初めから諦めるのではなく、認知度には波のような変化もあり、たまたま診察のときに調子がよくなかったということもあるので、自信を持って伝えるだけは伝えてほしいところです。しかし、よく理解できない患者に話をすることで患者がどう感じるかについての心配はあるでしょうし、どのように伝えるべきかという適切な方法がわからないということもあります。
こういった考えになるのも、認知症に対するネガティブな考え方があるからで、まずは意識改革から始めないといけないのかもしれないということです。