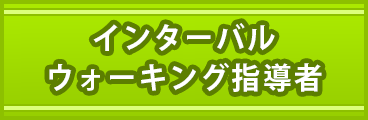国立高度専門医療研究センター6機関(国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター)が連携して、研究成果として「疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次)」を公開しています。提言のエビデンスの解説(第3回)を紹介します。
子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)は、性交渉により感染することが知られています。また、成功経験のある女性のほとんどが一生に一度はHPVに感染することがわかっています。国内調査では、細胞学的に異常のない女性の場合、15〜19歳で35.9%、20〜29歳で28.9%にPHVが検出されたと報告されており、特に性交渉の活発な年代ではごく普通にみられる感染といえます。感染しても多くの場合、HPVは自然に消滅する一方、繰り返し感染を起こします。
また、長期持続的に感染した場合に、細胞に障害(前がん病変)を引き起こし、その後、子宮頸がんに進展する可能性があります。しかし、HPV感染や、初期の子宮頸がんに特徴的な症状はありません。子宮頸がんは、その他のがんと異なり、20歳代後半から増加し、40歳代でピークを迎えます。ワクチンを接種するとともに検診を定期的に受診することが、子宮頸がんの予防と早期治療のために有効と考えられます。
2014年に出されたWHO(世界保健機関)の方針では、ワクチンを国のプログラムとして推奨しており、適用年齢の範囲は9〜13歳を第1の候補と定めています。子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種を導入した国では、接種した人は、接種しなかった人に比べ、進行がんの発生リスクが80〜90%程度低減されたという報告があります。日本で行われた4年間の追跡調査の結果では、日本人女性においてもHPVワクチンの効果が高いことに加えて、ウイルスの抗体価が一定期間持続することが示されています。HPVワクチン投与群と非投与群の間で、有害事象(深刻な副反応、新規の自己免疫疾患の発症、何らかの臨床症状)の発生頻度に差があるとはいえない結果が示されており、海外の知見を支持する結果となっています。ただし、厚生労働省の審議会で、「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛の発生頻度などがより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」とされ、積極的勧奨の差し控えを行っています。