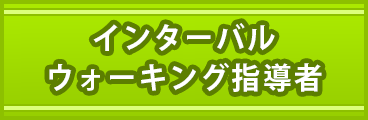日本の栄養学は終戦後の栄養不足の改善を目的とした“食物栄養学”から始まり、飽食の時代を迎えたときから生活習慣病予防を目的として体内機能に注目した“人間栄養学”へと変わりました。当時一緒に活動していた臨床栄養の研究者から「医者になったばかりのときに研究のために糖尿病患者を集めてくるように言われたが、探すのが大変だった」という話を聞きました。現在80歳を超えた先生ですが、それくらい糖尿病患者が少なかった時代から、今では患者は1000万人、予備群も1000万人を超えるところまで一気に増えています。
終戦後の日本の食事の変化は劇的で、1950年から1975年の間に牛乳は15倍、肉や卵は7.5倍、脂肪は6倍の摂取量となりました。不足しているものが補われているうちはよかったのですが、摂取が過剰になると生活習慣病(当時は成人病)が急激に増えて、食べるもののほうから食べる側の人間のほうに主眼が移りました。そして、栄養摂取によって身体で起こる機能変化の研究が盛んに行われるようになりました。その結果の一つとして現れたのが医薬品的な機能を有する健康食品の登場でした。
栄養学というと、どうしても栄養素が注目されがちですが、人間栄養学では食品の生産から食べ方まで研究範囲が広がりました。栄養素を充分に摂取しても吸収にも体内での使われ方にも個人差があり、これを研究していくと性差(男女差)、年齢に加えて、気候や生活環境、自律神経の働きや精神的な部分までが消化、吸収、循環、代謝、排泄にも関係あることが明らかになり、この一連の流れの中で栄養素が、どのように変化するのかがわかれば、それぞれの人の活動に合わせた栄養素の摂り方、活かし方がわかってきます。
このように自分たちの身体を統合的に見ていくのが全人的栄養学で、英語ではホリスティック(holistic)・ニュートリション(nutrition)となります。ホリスティックには全体のつながり、バランスの取れた行動という意味もあって、それぞれの臓器や器官と栄養素の関わりだけでなく、全身のネットワークとして栄養機能を見ていこうとするものです。
生活習慣病の予防・改善のための栄養学はほぼ完成形まで進んだとされていますが、発達障害の改善については栄養学の手が及んでいないところも多くあり、成長を進めながらの栄養改善には、まだまだ研究すべきところが数多くあります。そこにチャレンジしていくのも全人的栄養学の役割だと認識しています。